地震・火災から身を守る(1) 地震の揺れから身を守る
配信

激しい揺れでは何もできない・・・。
かなり以前から「地震の時は冷静に身を守る行動を」と言われています。しかし、どのような行動で身を守れるのか、正しく理解されてきたのでしょうか。
過去の地震や実験データを総合すると、人間が意思通りに行動できるのは、せいぜい震度4くらいまで、冷静さを保てるのも震度4くらいまでと言われています。
言い換えれば、震度5弱以上になると、行動が制限され、冷静な判断ができにくくなるということです。
さらに、それくらいの震度になると、不安定な家具の転倒や、棚の上の物が落下したりします。
つまり、震度5弱以上の揺れは、普段考えていることとまったく違う状況、経験したことのない困難な状況をもたらしてしまうのです。
これまで、適切だと思っていた地震時の行動を見直してみましょう。
身を守る行動の流れ
地震は最初から100%の激しさで揺れ出すわけではありません。直下型の地震でも僅かですが、最初に微小な揺れの時間帯があります。
そこで、地震時における行動を、図のように3つの時間帯に区分して考えることにしましょう。

(1) 緊急地震速報を受信または初期微動を感じた
しかし、東日本大震災における仙台市では、強い揺れの、15秒ほど前に緊急地震速報を受信したという記録も残されており、このシステムを活用すれば、身を守ることに効果があるはずです。
そこで、まず、とるべき行動は、安全な場所へ移動し、身構えるということです。ガラス窓、食器棚、転倒危険のある家具の近くを避けましょう。そして、照明器具などの落下危険から頭部を保護することを考えます。
 また、揺れでドアの枠が変形し、閉じ込められてしまうことを防ぐために、避難経路となるドアを開けることも必要になってきます。
また、揺れでドアの枠が変形し、閉じ込められてしまうことを防ぐために、避難経路となるドアを開けることも必要になってきます。(2) 激しい揺れが襲ってきた
しかし、大半は、動くことさえままならない状況になってしまいます。そのようなときに無理に移動しようとすると、ケガに直結します。過去の地震の調査結果では、無理な行動が原因で負傷したケースが数多く報告されています。
そこで、転倒・落下物から保護する姿勢をとります。腕で頭を覆い、頭部を保護します。このとき、手を開いていると指のケガのもと。指のケガは、その後の行動に大きな支障を来します。手を握っておきましょう。
(3) 揺れが収まった
火の始末のほか、電気火災を防ぐためにブレーカーを落とすことも重要です。家具の転倒や落下物によって、コードが傷ついて発火したり、電気器具のスイッチが誤って入ってしまうことが考えられます。これらの出火を防ぐために一時的に電気を遮断しておくのです。余裕ができて、部屋の安全が確認できたらブレーカーを戻します。
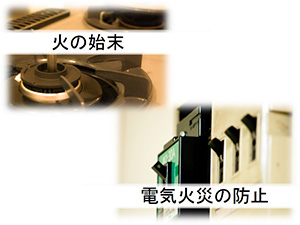
地震は不意に襲ってくることを忘れない
起震車による訓練を体験したことがありますか?
自治体が協力して実施される防災訓練などでは、こうした震度体験をできるケースが増えています。積極的に参加してください。震度7という激しい揺れが理解できるはずです。
しかし、重要なことは、その激しい揺れが不意に襲ってくるということです。調理中、食事中、入浴中、そして就寝中かもしれません。そのときに、果たして冷静に身を守る行動がとれるでしょうか。
いざというときの行動は、事前にしっかりと考え、準備したことの延長線上にあります。普段から、適切な行動とはどういうものかを家族で話し合い、頭の片隅にでもとどめておくことが大切です。できれば、簡単な行動マニュアルをつくっておき、忘れたころに家族全員で見直していただきたいですね。
一方では、人間の行動に限界があることを忘れてはいけません。
そのために重要な「安全な空間をつくる」ことを次回は考えていきます。

執筆
永山 政広(ながやま まさひろ)
NPO法人ライフ・コンセプト100 アドバイザー
消防官として30年間にわたり災害現場での活動、火災原因調査などに携わり、2013年からNPO法人ライフ・コンセプト100のアドバイザーとして、セミナーや防災マニュアルづくりなど、マンション防災の第一線で活躍。